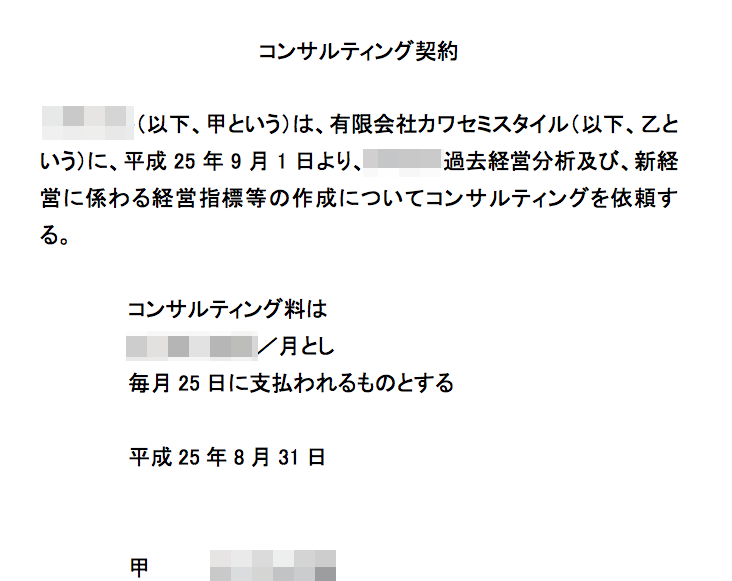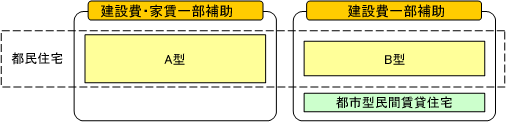たなくら ちあき。
間引きリンゴの魅力発見プロジェクト
摘果<てきか>に初挑戦
積極的にご協力している「小野りんご園」さんに8月初旬にうかがい、「摘果<てきか>」を行いました。
毎年GW<ゴールデンウィーク>に行っていて、もう4年になる「摘花<てきか>」とは違った趣に、緊張しました。

花を間引く「摘花<てきか>」は、幹から延びた細い枝に咲く5つの花からひとつを残す作業です。
小学3年生くらいになると、作業を理解して、楽しみながら手伝うことができます。すぐに飽きますけど。
ちょうどエアキャップ(ぷちぷち、梱包の緩衝材)を親指で潰していく感覚に似ているので、GWの日差しと吹き抜けるそよ風の中で、大人たちは黙々と集中するのです。

今回挑戦する「摘果<てきか>」は、その選ばれし花が、受粉によって膨らみ、ちょうど、ゴルフボールの一回りか二回り大きいサイズのものを、周りの実との栄養のバランスなどを考慮しながら、間引いていく作業です。
小野家のご長男に説明してもらいながら、まずは、はっきりと間引いていいものから、手に取っていきます。
毎回、農園に出て作業を手伝う際は、これからのイベントのことや、試そうと思う改善点、将来の方向性の話などをじっくり話す機会で、この時も舌の滑り出しはなめらかでした。
しかし、摘果はというと、私のレベルで判断できるような実は、あまり残っていなく(実は、摘果はひとつの木を1度にやるのではなく、数日に1度目立つものを間引く作業を繰り返すので、私が担当した木も、すでに何度目かの摘果でした。)、後は樹木のことや収量のこと、加工品に回すなどの目的を考えながらの作業になるため、素人の私には容易に手を出せるものではありませんでした。

約5時間で、クーラーボックス一杯の青りんご
実際に赤く色づいて収穫する収量の、倍から3倍くらいの量が摘果されるのではないかと思うほど、除草剤を使わないためにふかふかの雑草が生い茂る足元に、たくさんのりんごが落ちています。
今回の目的は、摘果したりんごを持ち帰ることですので、きれいな実だけれど、間引かざるを得なかったものを、持参したクーラーボックスに入れていくと、あっという間にボックス一杯の新鮮な青りんごを手に入れることができました。

まずは、ジャムと渋抜き
家に持ち帰って早速試食をすると、渋みが口の中に残り、皮も固めで、このままでは食べられません。
ジャム、ピクルス、そして渋抜きに挑戦してみます。
ジャムはいたって普通
二種類のジャムを作成して見ましたが、りんごの甘い風味が感じられず、また渋みも残るので、あまり勧められるものではありませんでした。

ピクルス・塩麹漬け
赤ワインで漬けたものや、塩麹で漬けたもの、他の野菜と一緒ならもしかするとましだったかも知れませんが、敢えてピクルスにする必要性は感じませんでした。

渋抜きをしたもの
焼酎とたまたま余っていたウイスキーで渋抜きをしてみました。
取りあえず、思った以上に渋が抜けたので、残ったものをすべて渋抜きにしてみました。

さて、結果は如何に。続きは後日また。
ホルダー型消火器にぶつけないで
この記事は、ブログ再編成のため新しいブログに移転しました。
自動的に移動しない場合は、こちらをクリックしてください。
私が管理するマンションの廊下には、各階に2本ずつ消火器が設置されています。
エレベーターホールから約3mの場所と廊下奥から5mくらいの場所です。
それぞれ廊下の床から10cmくらい高い場所のホルダーに収められているのですが、たまに曲がっているのが発見されます。
引越業者なのか、宅配業者なのか、ぶつけるのが原因と考えられます。
その都度、管理人が気づいて直してくれるのですが、先日もぶつけられていたという報告がありました。

「とっちゃえば?」
いつもの私の無責任な発言です。
エレベーターホールに床置きしたら、邪魔にならないでしょ。
建物管理の担当者が、すぐに確認してくれました。
20mに1本あれば、消防法上問題ないとのこと。従来の場所からエレベーターホールへ移動すると、もう一本との距離が開きますが、もちろん20m以上開かないので、OK。


ということで、試しに1箇所移動してみました。
ホルダーを外した所がきになるなぁ。
ということで、

プラスチックのキャップを購入。
ネジに挟んで、埋め戻して終了。
ただ、これで終わらないのが、いつものこと。
2箇所、どうしてもネジが緩まない。
仕方が無い。だれか業者が来た時に頼もう。
災害用排便処理袋60箱が届く
この記事は、ブログ再編成のため新しいブログに移転しました。
自動的に移動しない場合は、こちらをクリックしてください。
災害用排便処理袋が届きました。60箱。
3月20日に当ビルで行った「もちつき×サバイバル」(チラシ参照)では、区役所の地域防災課から招いた方のお話で、災害用トイレの重要性を認識しました。
イベント後、地域防災課の方が薦める災害用トイレは、代理店の現状の取り扱い(当時)がなく、メーカーから直接購入するべきだと知り、見積りを依頼しました。
さて、決済を受けて即導入。とならないのが賃貸物件の特徴なのかも知れません。
例えば、知人で所有マンションの管理組合の理事に、このイベントの話をした所、その一週間から10日後には、「理事会で購入を決めた」という知らせが届きます。
この大田区のマンションの前、練馬区の大規模団地の理事会でも、知人からの問題提起の結果、導入が討議され、結果、購入が決まりました。
あれ? うちのマンションは何で、決済されないの?
限られた家賃の中で、賃借人に必要以上のサービスをする必要はないという、固定観念が導入の障壁となり、私は、災害直後に災害用トイレを使いはじめるような、災害対策をしなかった場合、建物に起こる被害を説明しなければ、なりませんでした。
《災害用トイレを使わず、トイレを流しちゃった時の修繕費》 => 《災害用トイレの購入代金》
この式を用いて、説明しないと、オーナーには、理解してもらえないのです。
もし、この間に災害が起きたらその場合は仕方ない。このように納得するようにしていました。
そんなとき、大阪北部の地震。
報道を見たオーナーが、一言、災害用トイレの必要性に触れた!
今こそ買いましょう!
先のイベントでは、最適な保管場所ナンバーワンは、それぞれのお宅。
それを、客席で聞いていたオーナーは、退去時に持って行かれたらどうするのか? ただで渡す必要は無い。というのが、懸念事項でした。
気持ちが傾けば、こちらのもの。事前に渡す分は、入居時の設備として、エアコンやガステーブルと同じ扱いにする旨をあらためて説明すると、決済を受けることができたのです。
さて、この60箱ですが、メーカー担当者との事前のやり取りにも係わらず、納期の知らせがなく、ある日突然、しかも私の不在時に届きました。
この顛末については、また別の投稿で。
この60箱は、この投稿当時、集会室に鎮座しております。

双葉郡浪江町の「豊嶋歯科医院」ウェブサイト制作
日本コンサルタントグループ|WEB|
コンサルティング会社様ならびにブランディング担当の方からのご発注。
デザインやウエブサイト構成は、先方から支給。
通常の制作の他に、診療所の先生と浪江町副町長のインタビューの文字起こしを行いました。
田村市郡山市の整体氣功術「心海」ウェブサイト制作
日本コンサルタントグループ|WEB|
コンサルティング会社様ならびにブランディング担当の方からのご発注。
デザインやウエブサイト構成は、先方から支給。
通常の制作の他に、診療所の先生のインタビューの文字起こしを行いました。
また、お客さまの声は、co-ba koriyamaのご協力を得て、3名の方を手配することができました。協力体制づくりから、実際の施術スケジュールの調整や感想文の手配などを行いました。
12/1 ネット講座@オルデュール(東中野)
本日のネット講座「Office編」では、
・Excelの基本初回「セル、列、行、罫線、ctrl+1」
・記録用の表をWordで作成
でした。
ちゃんと成果をお持ち帰りいただきました。
11/24 ネット講座@オルデュール(東中野)
本日のネット講座「スマホ、タブレット編」では、
・LINEのコメントの消し方
・Androidタブレットでのワンセグの視聴方法と鮮明な画像受信の手段
・Youtubeアプリの利用方法について(質疑応答)
でした。
都民住宅 一括借上契約終了の物語 第1話
一括借上契約終了にともなう事業相談は、突然始まった。
都民住宅とは
国の「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成5年7月施行)を活用し、広さ、設備など一定の基準で建設された、中堅所得者層向けの良質な賃貸住宅です。国の制度である特定優良賃貸住宅(特優賃)を東京都では「都民住宅」と呼んでいます。
国と東京都から入居者の家賃負担を軽減するために建設費と家賃の一部補助が行われている住宅(都民住宅A型)と建設費の一部補助が行われている住宅(都民住宅B型・都市型民間賃貸住宅
)があります。
現在、都民住宅、都市型民間賃貸住宅の新規建設は行っておりません。
平成25年(2013年)8月某日。
その依頼は、暇を持て余していた私を見かねて、根回しをしてくれた方からのありがたい申し出で始まりました。
都民住宅の一括借上終了を平成29年3月に迎える物件について、一緒に考えてほしいというのがその内容でした。発注元のオーナー様はさらにありがたいことに、わざわざ契約書を作成して押印してくれたのです。


定例会への出席
平成25年(2013年)9月第一週から、毎週一回朝9時30分からの定例会に、必ず出席する日々が始まりました。
そして、それはすぐに、毎週一回、私の作業の進捗状況を報告する場となり、私の提案場となり、オーナーとそのご家族のコンセンサスを得る場所となっていったのです。
私が経営修士(MBA)の資格を有しているとはいえ(筆者経歴参照)、海の物とも山の物ともつかない状態で、よくご英断いただいたものだと、今になって思えば感謝するとともに、期待を裏切らないように毎週必至だった当時を思い出します。
コンサルティング開始当初、都民住宅 一括借上終了に対して行ったこと
●契約条件の一覧
●「家賃等振込金額通知書」の入力
●「家賃減額補助通知書」の入力
まず、契約書を拝見し、契約条件の一覧表を作成しました。
次に、東京都住宅供給公社様から毎月送られてくる、「家賃等振込金額通知書」を4年前の平成21年(2009年)に逆上って、表計算ソフト(Excel)に入力しました。なぜ、4年前かというと、たまたまお借りできるファイルがそこからのものが綴られていたからです。
同様に、「家賃減額補助通知書」の内容も平成21年(2009年)から、各戸の変遷を記録していきました。
賃貸住宅の規模
ここで、私が相談を受けた賃貸住宅の規模ですが、差替えがない範囲でいうと、東京都住宅供給公社様が管理する都民住宅の規模で言えば、1棟あたりの平均戸数より多い規模だと思います。
ですので、過去4年に逆上って、記録を入力する作業はそれなりの労力を必要とする作業でした。
賃貸マンション事業を経営面から把握する
4年分の通知書の入力には、ご契約いただいたコンサルティング料の範囲で、ほぼ3ヵ月〜5ヵ月を掛けました。
この作業によって、担当する賃貸物件でどんなことが起きているか、つぶさに理解することができました。
単に金額を入力するのではなく、通知書の一件一件に目を通して、どんな作業にどのくらいの費用が掛かっているのかを理解し、またそれが、4年間でどのように変化しているのかを、知識として蓄えることができました。
ありがとうの報告会を開催!
多くの都民住宅の賃貸物件のオーナーがそうであるように、私が担当する物件も、相続対策の目的で個人所有の土地に建てられた物件でした。建築当初にオーナーがリスクを考えて、悩んだ末に契約したことで、契約期間中のオーナー家族は安定した収入を得、子どもは学校に行き、家族はたまには贅沢に外食を楽しんだのかもしれません。
それもこれも、あの時判断をしてその後も維持に心を砕いてきたオーナーの孤独な戦いの結果だということが、前述の分析から分かってきたのです。
作業開始から3ヵ月が過ぎた頃、定例会で私はひとつの提案をしました。
「この春に、家族会議を開いていただきたい。そして、そこで私からご報告をしたい。その内容は、オーナー、今までありがとうという内容になるはずです。」
私は、この家族会議をひとつのきっかけにしようと考えていました。
契約書に記載されているもう一つの役割「新経営に係る経営指標等の作成」を作成しご提案するきっかけです。
それは単なる経営分析ではなく、地域性・時代性そして事業承継を睨んだ経営指標のご提案を行うつもりだったのです。
平成26年4月の家族会議に向けて、書類が積み上げられた机の前を離れて、賃貸マンションの現状を探るべく、街へ出たのです。
次回、第二回「東京都住宅供給公社様とのはじめての打ち合わせ」は、2016年11月初旬更新予定です。
TVアニメ『チャギントン』公式ホームページ リニューアル
フジテレビ|WEB|
放送開始から担当させていただいているウェブサイトを先日リニューアルしました。
それまでの、バリバリのFLASHから一転スマホ対応を強化したサイトに仕上げました。
毎週日曜日と月曜日に、必ず更新してます。